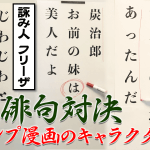コアラのマーチを開封せずに10000回振ると中身が凄いことになるらしい!?みんながやってる面白企画!今回は我々もその結果の真相を追求してみました!!

PM 17:30 中野駅
あいつと話すのは何年振りだろう。
十日ほど前の晩、ろくに動きもしないSNSにいきなり連絡をよこしたあいつは、学生時代の青春のほとんどを共に過ごした馬鹿な男だった。

クラスでもお調子者の俺とあいつは、学業もそこそこにギターをかき鳴らして、ロックミュージックにどっぷり浸かっていた。
進学を期に道を違えてから自然と会わなくなったが、大した考えもなく大学に就職に進む俺は、安定を捨てて音楽一本で食っていく道を選んだあいつを、心のどこかで羨ましく思っていた。

聞けばあれからずっとバンド活動を続けており、都内のライブハウスにも出演していたという。
まさかあいつと東京で飲むことになるとは。

「よおジュン!」

「おお、エータ!元気してたかよ」

「それなりにな。お前はすっかりサラリーマンって感じだな。つか大丈夫かよ、こんな時間に抜け出してきて。」

「ああ、うちその辺緩いからさ。抜けた分、土日でちょちょっと仕事すれば大丈夫だから。」

「土日もやんの?社畜じゃねえか!」

思えばあれから色んなやつと出会ったけど、親友と思える存在は後にも先にもエータだけだった。

馬鹿みたいに夢を追い続けるエータといると、あの頃の何でもできる気がしていた自分を、少しだけ取り戻せるんじゃないか。
そんな風に思えて、心臓が早鐘を打っている自分に気づく。

「じゃあまあ店入るか。普通の居酒屋でいいよな。」

「そのギター、練習帰り?」
「ああ、ライブ近くてさ。あ、こっち右な。」

「おっし、じゃあお疲れぇ!」
「お疲れーっす!」

早上がりして飲むビールの旨いこと。これ、定期的にやろうかな。

「いや〜!つーかあれだな。俺ら一緒に酒飲むのも初めてじゃね?」

「会うの高校以来だもんなあ。あっ、でも金麦飲んだじゃん。ほら文化祭の夜の」

「おい、あの夜の話はやめとけ。」

「……飲みすぎて、ミキちゃんの前でゲロった話?」
「おい思い出させんなって!ガチでトラウマなんだよあれは」
「フハハッ!お前狙ってたもんなミキちゃん。せっかく文化祭のステージは大成功だったのに。」

「あの日俺はなあ、お酒はちゃんとハタチになるまで飲まないって誓ったんだよ。」
「ぜってえ守ってねえだろw」
やっぱりエータとの馬鹿話は楽しい。
俺が大学から無気力気味になってしまったのは、お前といたのが楽し過ぎたせいじゃないか。
なんて、ふざけた責任転嫁をしてしまいそうな自分に、つい呆れてしまう。

「つーか二人でやってたのにお前だけいっつもモテやがってよお。ボーカル俺だぞ。」
「そんなことねえって。お前の方が今モテてんだろ、バンドマンだしさあ。」

「ファンとかどんくらいいんだよ」
「んー、ファンっていうあれじゃないけど。今度のライブは100人くらいは集まってくれるな。」
「えーーすげえじゃん!やっぱすげえなお前羨ましいわ!!」

「いや全然よ全然、つーかお前も音楽やりゃいいじゃん!あれからどうなのよ、やろうと思ったりしねえの?」
「あー音楽なあ……」
「なんだったら俺らでもっかいやるか?スピリタス復活か!?」
「するわけねえだろw」
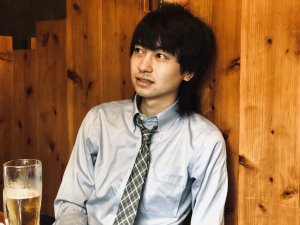
「いやあもう、スピリタスのメジャーデビューの夢はお前に託したんだって。応援してるぜ。」
「全然ライブ来たことねえじゃんw」
「いや知ってたら行ってたってマジで!あれから連絡しなくなったしさあ。あれ、今のバンド名なんだったっけ?」

「ハイウェイズな。」
「あーーそうだ!ハイウェイズだハイウェイズ。」
「Twitterとかもやんないんだもんなーお前。いやあ、よく声かけれたよほんとに。」
「Facebookのメッセージなんか久々に開いたっつーのw」
「そうそう、そんでさ。」

「ライブ、来てみない?」

「あー、ライブか〜。」

「次のライブ、結構気合い入れててさ。マジで見に来てくれよ。俺の招待って言えばタダで入れるからさ。」

「……ちょっと予定確認してみるよ。いつなの?」

「来週の日曜なんだけど、ああ時間と場所送るよ。」
「あざす。じゃあちょっとまた返事するわ。」

結論、その日は丸一日空いていた。
ただなぜか、親友の晴れ晴れしい舞台に、俺は行くと即答ができなかった。

その後は、地元の駅で勝手にゲリラライブをやって警察に追い回されたこととか、放送室に乱入してライブの告知を無理やりやったこととか。
あの頃の俺たちの武勇伝を一つ一つ挙げていっては、こそばゆくも誇らしい思い出の確認作業を終電までやり合った。

エータが彼女の親に顔合わせしに行って、二秒で帰れとブチ切れられた話なんかを聞いて、ゲラゲラと笑った。

だけど、ライブに行くよと言えなかったその理由はよく分からず、ケータと別れるまで、それは胸につっかえたままだった。
AM 16:15 新井薬師
さっきからだらだらと、よく知らない町を歩き続けている。

今日はエータのライブの当日。会場もどうやらこの辺りらしい。
だが、開演時間はとうに過ぎている。

俺はあれからずっと、あのときの胸のつかえについて考えていた。
そして逡巡しながら、自分のひとつの気持ちが徐々に縁取られていくのを感じた。

俺の中には、もう一人の俺がいた。
あいつと一緒に音楽をやっていく俺が、ずっといたんだ。

俺の本当の姿は、あいつと一緒に歌ってる俺で。バンドでちやほやされている俺で。かっこいいステージに上がっている俺で。
現実にいないけど、あり得たかもしれないもう一人の俺を、ずっと心の拠り所にして生きていた。

俺は、あいつとステージに立っている俺が、本当の俺じゃなくなってしまうことを恐れていた。
だから、勉強にもサークルにも、仕事にも、恋愛にも、本気になれなかった。

そして、あいつが俺以外と頑張っている姿も、見ることができなかった。

ただ、

それじゃ駄目なんだ。

あの頃が一番楽しかったなんていつまでも言い続けて、ずっと頑張らないなんて、死ぬほどだせえ。

現在進行形で夢を掴もうともがいてるあいつを見て、そう思えるようになった。

だから俺は、エータのライブを観る。
エータの一人のファンとして、自分を重ねずにエータを応援する。

エータを応援することで、自分自身も前に進める気がする。
あいつが俺の分まで夢を叶えてくれそうな気がしてならないんだ。

とにかく今日はあいつの勇姿をこの目で見届けてやろう。
俺の人生がかかってるんだ。しょうもないライブだったら承知しねえぞ。

俺は腹を括って、目の前の看板を睨んだ。

そこには、解散ライブと書かれていた。



「あ、こんにちは〜。」

「取り置きですか〜?」

「いや……」

「招待であれば、お名前と、招待を受けたメンバーの名前を教えてください。」

「あ、その……。」

「……?」

「当日券、買います。」
「あ、はい。ありがとうございます〜。」

「3,300円ちょうどいただきます〜。」

「ではすでに始まってますので、お静かにお入りください。」











出口に一番近かった俺は、ライブが終わったあと出待ちもせずに会場を後にした。

解散の理由は、音楽性の違いとかかっこいいものじゃなく。
正社員になるメンバーがいるとか、結婚を考えているだとか、至極現実的な事情が並べられていた。

バンドとしての魅力は、正直よく分からなかった。
あれから年月も立って、俺の好みも変わったのかもしれない。

ただそれでも。

エータの歌には、力が宿っていたし。

最後の曲は、

俺らが昔作った歌に、よく似ている気がした。

「ジュン!」


「…エータ。」

「よお、来てくれたんだな。」

「びっくりしたか?まあ、そんな感じで。俺もこれからはサラリーマンだわ。」

「……。」

「ちょっと歩かね?」

「お前なんで黙ってたんだよ、解散って。」

「解散ライブとか言ったら、さすがに誘い断りづらくなるだろ。」

「本当に俺の音楽が聞きたいなら、見に来てもらいたい。って思ったんだよ。」

「…相変わらずだな。」

「じゃあごめんな、声だけかけときたくてさ。そろそろ戻るわ。」

「それじゃあな。また、就活のこととか教えてくれよな。」


「おい」

「お前いいのかよそれで」

「さっきのバンド、もう解散みたいだから言うけど、お前だけはまだ光ってたぞ。」

「せっかく才能あんのに、諦めんなよ。もったいねえって。」

「音楽で食ってくんだろ?お前なら絶対できるって。今は配信とか色々……」

「お前は、降りたじゃねえか。」

「……。」

「安全圏からじゃ何とでも言えるんだよ。」

「自分は適当に受験して大学受かって、東京の会社で働いてよ。」

「そんなやつの言う夢を諦めるなって、何なんだよ。」

「俺は……」

「覚えてるかよ、俺はあの日」
「腹、括ってたんだぜ」

「なあ、俺たちさ。」

「高校卒業したら、正式に音楽一本でやって行かねえか。」
「……。」
「俺らなら、スピリタスなら行ける気がすんだよ!」

「……俺は、大学いくよ。」

「え、何でだよ…。」

「いやまあ、大学はみんな行くからな。そこすらやめてってのは、ちょっとな。」

「……元々決めてたのか?」
「まあな。でも、俺エータの歌のセンスすげえと思うから、絶対成功すると思ってんだよ。」
「……そうか。」
「俺じゃなくて、もっと技術のあるやつらとバンド組むべきなんだよなエータは。マジで。」

「エータには俺の分まで、夢を叶えて欲しいんだよなあ。」

「いやあ、応援してるぜ。マジで。」


「スピリタスで、良かったんだぜ。俺は。」

「……。」

「……勘違いすんなよ。」

「これは俺の夢だからな。お前の夢じゃない。」

「俺の夢が終わったんだ。」

「じゃあな。」


















完